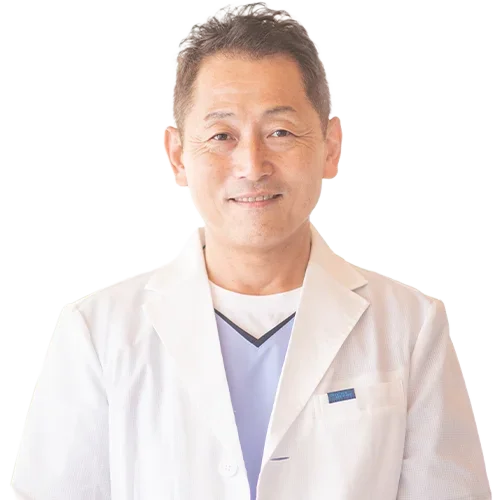ホスト:こんにちは。今日の深掘りはストレスです。もう現代人なら誰でも感じるこのストレスですけど、その正体って一体何なのか。 医学的、心理学的に核心に迫っていきたいと思います。
ゲスト:今日のミッションは、そのストレスの知識を、こう単なる情報じゃなくて、皆さんの実感とつなげられるような、そんな形でお届けすることですね。
ホスト:なるほど。早速ですけど、ストレスってもともとは物理学の言葉だったとか?
ゲスト:ああ、そうなんですよ。面白いですよね。それを医学の分野に持ち込んだのがカナダのセリエ博士なんです。で、大事なのはストレッサー、つまりストレスの原因になるもの。まあ、寒さとか騒音とか人間関係とかいろいろありますけど、それと、それによって体の中に起こる反応。これをストレス反応って言って区別したことなんです。
ホスト:あ、原因と反応は別物なんですね。
ゲスト:ええ。で、セリエ博士が発見したのは、どんな種類のストレッサー、原因に対しても、体はある程度こう共通の反応を示すってことなんですよ。
ホスト:へえ、共通の反応ですか?具体的には体の中で何が起こるんですか?ストレスを感じると。
ゲスト:まず脳が、「お、何か来たぞ」と認識するわけです。
ホスト:はい。
ゲスト:それが大脳辺縁系っていう感情に関わる部分に伝わって、不安とか怒りとかが生まれる。その信号が視床下部っていう司令塔に伝わると、主に二つのルートがこう、わっと動き出すんです。
ホスト:二つのルート。
ゲスト:はい。一つはあの自律神経系、特に交感神経ですね。こっちは早い反応で。
ホスト:早い方。
ゲスト:ええ。アドレナリンとかが出て心臓がドキドキしたり、血圧が上がったり。いわゆる闘争逃走反応の準備です。
ホスト:ああ、戦うか逃げるか、みたいな。
ゲスト:そんな感じです。で、もう一つが、少しゆっくりした反応で内分泌系ホルモンのルートですね。
ホスト:ホルモンですか?
ゲスト:ええ。いわゆるHPA軸、視床下部下垂体副腎質系って呼ばれるものです。
ホスト:HPA軸。
ゲスト:ここからコルチゾールっていう、まあ代表的なストレスホルモンが分泌されます。
ホスト:コルチゾール。
ゲスト:これが血糖値を上げたりしてエネルギーを供給したり。あと、短期的には炎症を抑えたりもするんですけど。
ホスト:ストレスが溜まると風邪ひきやすくなるとか言いますけど。それってこのコルチゾールと関係が?
ゲスト:まさにそこなんですよ。コルチゾールも出続けると、今度は免疫細胞の働きをちょっと抑えちゃうことがあるんです。
ホスト:え?抑えちゃうんですか?
ゲスト:ええ。だから慢性的なストレスっていうのは体の抵抗力、例えばNK細胞の活性とかを弱めてしまって、感染症にかかりやすくなったりする可能性が指摘されてますね。
ホスト:なるほどな。体の反応はだいぶ分かってきましたけど。でも同じ出来事があっても全然平気な人もいれば、ものすごくダメージ受ける人もいますよね。その違いって何なんでしょう。
ゲスト:そこがまた、ストレスの面白いところで、非常に重要なのが認知、評価。
ホスト:認知、評価?
ゲスト:ええ。つまり、目の前で起きた出来事をその人がどう捉えるか。これは大変だ、脅威だって思うか?よし、乗り越えてやろう、挑戦だって思うか?
ホスト:ああ、捉え方次第で。
ゲスト:そうです。その捉え方。 意味づけによって、その後のストレス反応の大きさとか質が変わってくるんです。性格とか、これまでの経験、自分に自信があるかとかも影響しますね。
ホスト:なるほどね。じゃあ、その捉え方以外にも個人差を生む要因ってありますか?
ゲスト:もちろん対処の仕方も人それぞれですね。「コーピング」って言いますけど。問題そのものを解決しようと頑張るタイプ、「問題焦点型」もいれば、まあ気分転換したり、誰かに話を聞いてもらったりして、そのストレスによる嫌な感情を和らげようとするタイプ「情動焦点型」もいます。
ホスト:うん。どっちが良いとかじゃないんですね。
ゲスト:ええ、状況によりますね。あとはやっぱり、周りのサポート。家族とか友人とか、そういう社会的支援があるかどうかもすごく大きいです。
ホスト:確かに一人で抱え込むと辛いですもんね。あの、生活習慣も関係あります?
ゲスト:密接に関係しますね。ストレスを感じている時って、体はビタミンCとかB群タンパク質なんかを結構消耗しやすいんですよ。
ホスト:へえ、消耗するんだ?
ゲスト:だから、バランスのとれた食事っていうのは、ストレスへの抵抗力をまあ、支えてくれるわけです。
ホスト:なるほど。
ゲスト:運動も。特に有酸素運動なんかは気分転換にもなりますし。脳内で「エンドルフィン」っていう。 こう、ちょっと幸福感を感じさせる物質が出るとも言われてますね。
ホスト:ああ、運動するとスッキリするの、そういうことか。
ゲスト:で、逆に睡眠不足とか不規則な生活、飲み過ぎ、タバコの吸いすぎ。こういうのはストレス耐性を下げますし、ストレスが原因でまた生活が乱れるっていう悪循環にもなりやすい。
ホスト:んー悪循環。
ゲスト:それがやっぱり、生活習慣病のリスクを高める一因にもなるわけです。
ホスト:なるほど。あともう一つ興味深かったのが、ライフサイクル、人生の段階によってストレスの性質とか影響が変わるっていう視点です。
ゲスト:ああ。エリクソンの発達段階説が参考になりますね。
ホスト:エリクソン?
ゲスト:ええ。人生のそれぞれの時期に特有の心理的な課題っていうのがあるんです。例えば思春期だったら自分って何だろうっていう自我同一性の問題とか。成人期なら仕事とか家庭での役割、責任。 老年期になると喪失体験とか、そういうテーマが出てきます。
ホスト:その課題を乗り越えるのが、ある意味ストレスでもあると。
ゲスト:そうですね。で、それはうまくいかないと、その時期に特有の、まあ、ストレスに関連した病気が出やすくなると考えられています。
ホスト:例えばどんな?
ゲスト:学童期なら不登校とか。思春期、青年期なら摂食障害とか引きこもり。成人期ならうつ病、突発性難聴とか。あとは高血圧とか心身症。老年期もうつ状態とかですね。
ホスト:うーん。 年代ごとに、いろいろな形で出るんですね。 でも、同じようなストレスを受けても胃にくる人もいれば、なんか血圧が上がる人もいるじゃないですか。症状の出方が違うのはなんでなんですか?
ゲスト:それはですね、慢性的なストレスで体のバランス、「ホメオスターシス」。それが崩れて病気になる時に、どの臓器に影響が出やすいかっていうのは、個人の、まあ遺伝的に決まっている弱点みたいなものが関係してるんじゃないかと。
ホスト:弱点。
ゲスト:ストレスっていう負荷がかかった時に、その人にとって、もともと弱い部分に症状が出やすいっていう考え方です。
ホスト:なるほど。体質みたいなものも関係するわけですね。
ゲスト:ええ。そういうことです。
ホスト:いや、今回の深掘りで、ストレスって単に嫌なことっていうだけじゃなくて、私たちの捉え方とか行動とか生活習慣、それから人生の段階ともすごく複雑に絡み合ってる、心と体の反応なんだなっていうのが見えてきました。
ゲスト:そうですね、特にやっぱり客観的な出来事そのものよりも、それを私たちがどう認識して評価するかっていう主観的な側面がすごく大きい。ここがポイントですね。だからこそ、慢性化させないように自分なりの対処法を知っておいたり、ケアしたりすることが大切になってくるわけです。
ホスト:本当にそうですね。最後に、これを聞いているあなたにもひとつ問いを投げかけてみたいんですが。
ゲスト:はい。
ホスト:ストレス反応に認知評価。つまり捉え方が大きく関わるということはですよ。起こってしまった出来事そのものは変えられなくても、それに対する自分の見方とか考え方をちょっと意識して変えてみることで、ストレスの影響ってある程度コントロールできるのかもしれないってことですよね。
ゲスト:ええ。可能性はありますね。
ホスト:あなた自身のストレスとの向き合い方について、これを機に少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれません。
※出典 メディカル・サイエンス・インターナショナル 「ストレス診療ハンドブック」