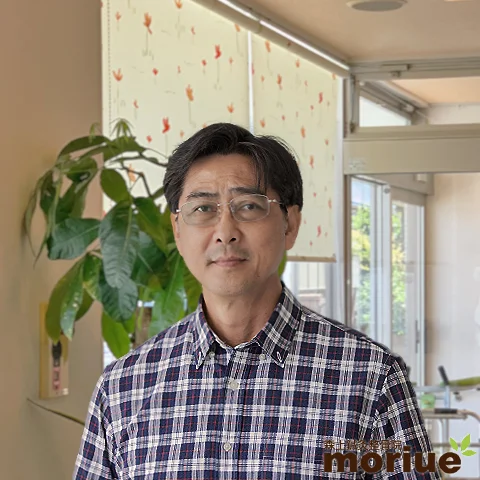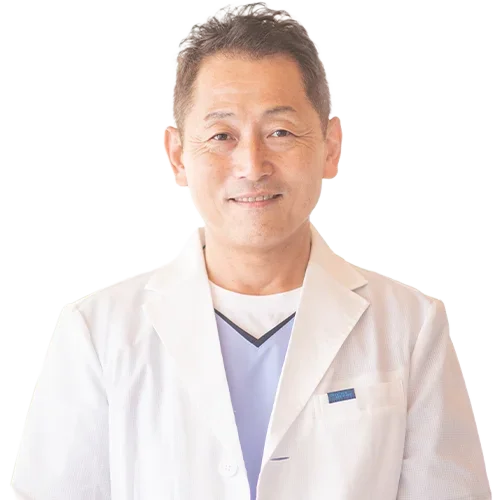ホスト:今日のテーマは突発性難聴です。
ゲスト:はい。
ホスト:お手元にある、えー「EBMから見た突発性難聴の臨床」、それから「急性感音難聴の診療の手引き」、あと森上鍼灸整骨院の治療に対する考え、これらの資料をもとにですね、大事なポイントを探っていきます。
ゲスト:ええ。
ホスト:ミッションとしては、この突然耳に起こる変化、これが一体どういうものなのか、回復の見込みは?そして、あなたが知っておくべきこと、これを明らかにしていきたいなと。
ゲスト:はい。
ホスト:よし、じゃあ早速核心に迫りましょうか。
ゲスト:お願いします。えっと、突発性難聴というのはですね、まあ、その名の通りなんですけど、ある日突然、ほとんど片方の耳、まあ時には両耳のこともありますが、聞こえが悪くなる――そういう状態ですね。
ホスト:突然ですか……
ゲスト:そうなんです。原因については、まだはっきりとは分かっていない部分が多いんですが。
ホスト:うーん。
ゲスト:内耳の、例えば血流が悪くなるとか、あるいはウイルス感染、あとは自己免疫みたいなものが関わっているんじゃないかと考えられていますね。
ホスト:なるほど、原因が特定しにくい病気なんですね。それで治療後の経過について資料を見ると、まず「3分の1ルール」っていうのが、これ結構インパクトありますよね。
ゲスト:ああ、そうですね。これは非常に重要なポイントだと思います。治療を受けてもですね、完全に元の聴力に戻る方っていうのは、まぁだいたい3分の1くらいだと。
ホスト:3分の1ですか。
ゲスト:ええ。で、ある程度は良くなるんだけども、ちょっと後遺症が残ってしまうというのが、また3分の1。
ホスト:ふむふむ。
ゲスト:そして、残念ながら残りの3分の1は、治療してもほとんど改善が見られないと。これは厚労省の研究班の報告なんかでも、まあよく言われる一般的な傾向なんです。
ホスト:ということは、つまり、約3分の2の方には何かしらの症状がこう残る可能性がある。そういうことですか?
ゲスト:まさにそういうことですね。ええ。ですから、最初から「完全回復が当たり前じゃないかもしれない」というその視点を持つことが、大事になってくるかもしれませんね。
ホスト:なるほど。それは知っておくべきですね。具体的にはどういった症状が残りやすいんでしょうか。
ゲスト:そうですね。一番多いのは、やはり聴力の低下、つまり難聴です。
ホスト:はい。
ゲスト:それから、「キーン」とか「ジー」とか、そういう音が聞こえ続ける耳鳴り。
ホスト:ああ、耳鳴り。
ゲスト:あとは、耳がこう、詰まったような感じがする。いわゆる耳閉感。
ホスト:耳閉感。
ゲスト:ええ。で、発症した時にめまいがあった方だと、それが続くこともあります。
ホスト:うーん。
ゲスト:で、これらの症状って単に不快なだけじゃなくて、例えば会話が聞き取りにくくなったり、夜眠れなくなったり、集中力が落ちたりして、生活の質、いわゆるQOLをかなり下げてしまう原因になるんですね。
ホスト:QOLへの影響、大きいんですね。
ゲスト:ええ。それで、精神的にもこうストレスが溜まって不安になったり、時にはうつ状態になってしまうというケースも報告されています。
ホスト:いや、それは深刻ですね。治療については、資料を見るとタイミングがかなり重要だと。具体的な期限みたいなものも書いてありますね。
ゲスト:そうなんですよ。ここがポイントで、ステロイドの全身投与――飲み薬とか点滴ですね――これは発症してから、できれば2週間以内に始めるのが望ましいと。
ホスト:2週間。
ゲスト:ええ。で、もっと直接的に、鼓室、耳の中にステロイドを注入する治療法もあるんですが、これは発症後、まあ20日以内が目安とされています。
ホスト:20日。
ゲスト:一般的には、治療開始は早いほど回復の可能性が高まると言われています。
ホスト:はい。
ゲスト:ただ、これも絶対ではなくて、早く始めてもなかなか効かない場合もあれば、少し遅れても改善するケースももちろんあるんですが。
ホスト:なるほど。その回復の見込み、予後についてですが、何が影響するんでしょうか。年齢とか性別とか?
ゲスト:えっとですね、いくつか要因が挙げられています。まず、発症した時の聴力障害の程度。やっぱり症状が軽いほど回復しやすい傾向はありますね。
ホスト:ふむふむ。
ゲスト:それから、聴力検査の結果の波形。オージオグラムって言いますけど、その形。
ホスト:波形ですか。
ゲスト:ええ。低い音だけが聞こえにくいタイプとか、真ん中の音が谷のように落ち込んでいるタイプは、全体的に全部聞こえにくいタイプよりも、予後が良いことが多いとされています。
ホスト:へえ。
ゲスト:そして、もう一つ重要なのが、めまいを伴っていたかどうか。
ホスト:めまい。
ゲスト:はい。めまいがある場合は、聴力の程度が同じくらいでも、めまいがない場合に比べて予後があまり良くない傾向があるということがわかっています。
ホスト:それは、聴力の程度とは別なんですね。
ゲスト:そうなんです。独立した要因として考えられていますね。で、ご質問にあった年齢とか性別は、実は予後にはそんなに大きな影響はないとされています。
ホスト:なるほど、そうなんですね。ところで、資料の中には鍼灸院の視点もありましたね。標準治療で良くならなかった場合の、まあ選択肢として。
ゲスト:ああ、はい。森上鍼灸整骨院さんの資料ですね。これは耳鼻咽喉科でのステロイド治療など、標準的な治療を一通り受けたけれども、残念ながら耳鳴りとか耳閉感が残ってしまったという方々に対して、
ホスト:ええ。
ゲスト:鍼治療と、あとクラシック音楽を組み合わせたリハビリテーションを行うというアプローチを紹介していますね。
ホスト:鍼治療と音楽ですか。
ゲスト:ええ。これはもちろん標準治療の代わりというわけではなくて、その後の補助的な選択肢の一つという位置づけですけども。自律神経のバランスを整えたり、血流を改善したりすることで、残ってしまった症状による苦痛を少しでも和らげて、QOLの向上を目指しましょうという、そういう考え方ですね。
ホスト:なるほど。標準治療がまず基本で、その上でということですね。こうして全体を見てくると、結局、症状が残ってしまった場合にどう向き合っていくかという視点が、すごく重要になってきますね。
ゲスト:まさにおっしゃる通りです。聴力がある程度、もうこれ以上は良くならないというレベルで固定してしまった後、
ホスト:はい。
ゲスト:難聴とか耳鳴りが残った場合には、やはり患者さんのQOLを改善するためのリハビリテーションが推奨されています。
ホスト:リハビリテーションですか。
ゲスト:ええ。それには心理的なサポートとしてのカウンセリングであったり、あとは必要に応じて補聴器をうまく調整して使うフィッティングですね。そういったものも含まれます。
ホスト:ふむふむ。
ゲスト:残ってしまった症状と、上手に付き合っていくためのトータルなサポート体制が大事になってくるということですね。
ホスト:では、今回の深掘り、まとめてみましょうか。突発性難聴は原因がはっきりせず突然起こる。そして、約3分の2の方には何らかの症状が残る可能性があるということ。
ゲスト:そうですね。
ホスト:それがQOLとか心理面にも、結構大きな影響を与えると。
ゲスト:ええ。
ホスト:で、治療はとにかく早期開始が重要。そして、発症した時の聴力の程度とか、検査の波形タイプ、それからめまいの有無。これが回復の見込みに関わる要因だと。
ゲスト:はい。
ホスト:さらに、標準治療の後の選択肢として鍼のようなアプローチや、症状が残った場合のカウンセリングとか補聴器とか、そういうサポート体制もあるということを見てきました。
ゲスト:その通りですね。
ホスト:いやー、なかなか奥が深いですね。
ゲスト:そうですね。そこで最後に、ここまでの話を全部踏まえて、ちょっと皆さんに考えてみてほしい問いかけがあるんですが。
ホスト:おお、何でしょう?
ゲスト:この病気、標準的な治療を受けても完全には回復しないケースが少なくないわけですよね。
ホスト:ええ。3分の2は何かしら残る可能性があると。
ゲスト:そうなんです。だとしたら、治療のもっと早い段階から、例えば初期治療の段階から、長期的に見た時のQOL、生活の質をどう維持していくか、向上させるかっていう視点を、もっと強く組み込むことはできないだろうかと。
ホスト:なるほど。初期段階からですか。
ゲスト:ええ。例えば、症状が残る可能性も最初から少し視野に入れて心理的なケアを始めるとか、あるいはもっと個々の状態に合わせたリハビリ戦略みたいなものを、より早く、そしてもっと効果的に提供していくにはどうしたらいいんだろうか。
ホスト:うん、確かに。
ゲスト:すぐに答えが出る問題ではないかもしれませんが、少し立ち止まって考えてみる価値はあるんじゃないかなと思いますね。
※出典1 日本聴覚医学会 急性感音難聴診療の手引き 2018年版
※出典2 金原出版 SCOM033 EBMからみた突発性難聴の臨床