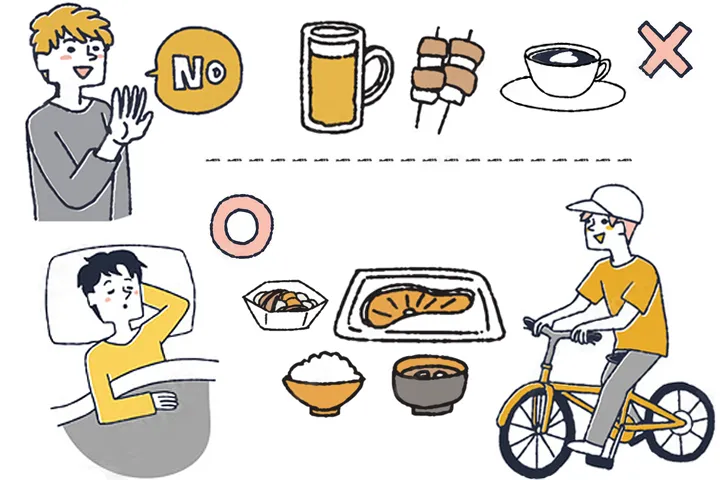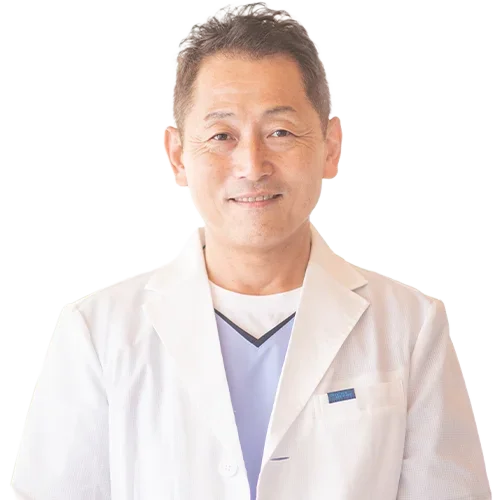ホスト: こんにちは。今回はですね、えーっと、急性低音障害型感音難聴、ま、ALHLとも呼ばれますけど、これについて、初めてこの名前を聞くという方にもわかりやすいように、基本からちょっと一緒に見ていきたいと思います。
ゲスト: はい。
ホスト: 「ENT臨床フロンティア、急性難聴の鑑別とその対処」、「病気が見えるvol.13、耳鼻咽喉科」 「森上鍼灸整骨院の考え」。これらの資料から、特に症状とか診断、あと治療法ですね。鍼治療の話も出てくるみたいなので、そのあたりも掘り下げていきましょうか。
ゲスト: ええ。そうですね。よろしくお願いします。
ホスト: では早速ですが、このALHL、資料を読むと、急に、しかも低い音だけがこう聞こえにくくなるっていう状態なんですね。
ゲスト: そうなんです。
ホスト: 特に20代から30代の、あのー比較的若い女性に多いという記述がありますね。
ゲスト: ええ、そうですね。で、これメニエール病ってありますけど、あれと同じで内リンパ水腫っていう内耳のまあ、むくみみたいなものが関係してるんじゃないかと考えられています。ただ、じゃあなんでそれが起きるのかっていうそのはっきりした原因っていうのはまだよくわかってないことが多いんですよね。
ホスト: なるほど。
ゲスト: よく耳にするあのー突発性難聴とはまたちょっと違うタイプなので、そこは区別が必要ですね。
ホスト: ふんふん。じゃあ具体的にはどんな症状が出るんでしょうか?自覚症状としては。
ゲスト: えっと一番多いのはやっぱり耳が詰まった感じ。それから「キーン」とか「ジーッ」とかいう耳鳴り。そしてもちろん難聴ですね。特に低い音が聞き取りにくいっていう。
ホスト: 低い音ですか。
ゲスト: ええ。それが割とこう突然起きることが多いようです。
ホスト: なるほど。 メニエール病だとあのぐるぐる回るめまいが特徴的ですけど、このALHLではそれはあまりないんですか?
ゲスト: 基本的にはその激しい回転性のめまいは伴わないことが多いとされていますね。ただ、ゼロではないですし、あと症状が繰り返す人もいるんですよ。
ホスト: あ、繰り返すこともあるんですね。
ゲスト: そうなんです。 だから診断には聴力検査がすごく重要になっています。
ホスト: 聴力検査
ゲスト: ええ、資料にある基準をすごく簡単に言うとですね、低い周波数の音、例えば太鼓の「ドンドン」みたいな音ですね。そういう音の聞こえがガクッと悪くなってる。
ホスト: はいはい。
ゲスト: でも高い周波数の音、例えば鈴の音とかそういうのは比較的ちゃんと聞こえている。
ホスト: へー、面白いですね。音の高さでそんなに差が出るんだ。
ゲスト: この特徴的なパターンがあるかどうか、まず見ますね。これがALHLを疑う大きなポイントになります。
ホスト: なるほど。で、繰り返す場合は、やっぱりその内リンパ水腫っていうのが有力なんですかね。資料に蝸牛型メニエール病っていう言葉もありましたけど。
ゲスト: そうですね。 特に症状が繰り返すケースでは、めまいはないけど、内リンパ水腫が原因と考えられる蝸牛型メニエール病の可能性を考えることが多いです。ただそれだけじゃなくて、例えば内耳の血流が悪くなってる内耳循環障害とか。
ホスト: 血流。
ゲスト: ええ、あるいはすごく稀ですけど内耳に小さな穴が開いちゃう、内耳瘻孔なんていう可能性も一応資料では触れられていますね。
ホスト: いろんな可能性があるんですね。
ゲスト: ええ。 そしてですね、複数の資料で結構共通して指摘されているのがストレスの影響なんですよ。
ホスト: ああ、やっぱりストレスですか。それは何か気になりますね。
ゲスト: そうなんです。ある資料なんかだと、このALHLになりやすい方って体がこう冷えやすかったりとか。
ホスト: 冷え?
ゲスト: はい。あとはまあ、神経が細やかというかそういう方が多い傾向があって、それがストレスと結びついてるんじゃないかみたいな考察もありますね。
ホスト: へえ~冷えとストレスですか?体質みたいなものも関係するかもしれないと。
ゲスト: ええ。そういう視点も、治療法を考える上でちょっと重要になってくるかもしれません
ホスト: なるほど。ではその治療法ですけど、これもいくつか書かれてますね。
ゲスト: はい。
ホスト: まずはその内リンパ水腫を考えて利尿薬、イソソルビドとか。 そういうお薬で体の余分な水分を出す。
ゲスト: そうですね。それが一つ。
ホスト: あと、突発性難聴にも使われるステロイド。でも、これは慎重にって書いてありますね。
ゲスト: ええ、まあ、炎症を抑える目的とかで使われることもありますけど、副作用とかもあるので、状況によりますね。
ホスト: なるほど。 他にはビタミン剤とか、あと血流を良くするお薬、ATP製剤っていうのもありますね。
ゲスト: はい、そういった薬物療法が一般的ですね。それに加えて、やっぱりすごく大事なのが心身の安静、ストレス管理ですね。
ホスト: ストレス管理、さっきの話にもつながりますね。
ゲスト: ええ。 で、さらにさっきの冷えとかストレスとの関連で、鍼灸整骨院さんの考え方を紹介している資料では、鍼治療についても言及されています。
ホスト: あ、鍼治療。
ゲスト: はい。特に体が冷えているようなタイプの方に、サーモグラフィーっていう、あのカラダ体表面の温度を見る機械とかで状態を確認しながら。 鍼で血行を良くして冷えを取ってあげる。そうすることで症状が良くなったり、再発も防いだりできる場合があるっていう考え方ですね。これはまたちょっと西洋医学とは違うアプローチです。
ホスト: 面白いですね。そういう選択肢もあると。治りやすさっていう点ではどうなんでしょう?
ゲスト: えーっとですね、比較的治りやすい面もあるとは言われています。ただ、再発も少なくないっていうのがまたちょっと厄介なところで。 資料によってはだいたい2割から4割くらいの人が再発するなんていう数字も出てますね。
ホスト: 結構な割合ですね。2割から4割って。
ゲスト: そうなんです。しかも再発を繰り返していくうちに一部の人、だいたい20%から25%ぐらいですかね。そのくらいの方は最終的にめまいも伴う典型的なメニエール病に移行してしまうこともある、という報告もあります。「一度良くなったからといってそれで終わり」 とは限らない場合があるんですね。
ホスト: うーん、なるほど。
ゲスト: なので、やっぱり長期的に経過を見ていくことと、あとはその誘因となりうるストレスであるとか、生活習慣ですね。そういったものの管理が非常に重要になってくるわけです。
ホスト: はい。治療に言及してた資料でも、なんか急にめまいが始まる可能性にも注意みたいなことが書いてありましたね。
ゲスト: ええ、そうなんです。やっぱりメニエール病との関連性っていうのは意識されているんだと思いますね。
ホスト: なるほどなあ。いやー今回、急性低音障害型感音難聴についていろいろ見てきましたけど、まとめると、急に低い音が聞こえにくくなるとか耳が詰まる感じとかの症状があって。
ゲスト: はい。
ホスト: 原因としては、内リンパ水腫が考えられるけどストレスも大きく関わってると。
ゲスト: そうですね
ホスト: 治療法も、お薬から生活指導。そして資料によっては鍼治療みたいなアプローチまで結構幅があるんですね。
ゲスト: ええ本当にそうですね 特に、こう一つの決まった病気っていうよりは、その人の背景にあるいろいろな要因、例えば水分のバランスだったり血流だったりストレス。あるいは、あの資料にあった冷えみたいなものですね。そういうものが複雑に絡み合ってる可能性が高いんだろうなというのが印象的でした。だから、診断も治療もその人ごとの根本的な原因にちゃんと目を向けていく必要がありそうですね。
ホスト: 本当にそうですね。 最後にこれを聞いているあなたへの問いかけというか、考えてみるきっかけになればと思うんですが。
ゲスト: はい。
ホスト: 資料の中で、真面目で几帳面、責任感が強い性格の人がなりやすい傾向がある、とか、やっぱりストレスが引き金になるっていう話が繰り返し出てきましたよね。
ゲスト: ええ、ありましたね。
ホスト: もしご自身で「あ、ちょっと当てはまるかも」と感じることがあるなら、普段、自分がストレスとどう向き合っているかなって少しだけ立ち止まって考えてみるのはどうでしょう。
※出典1 ENT臨床フロンティア 「急性難聴の鑑別とその対処」
※出典2 MEDIC MEDIA 「病気が見える Vol.13 耳鼻咽喉科」
※出典3 森上鍼灸整骨院 「治療に対する考え」