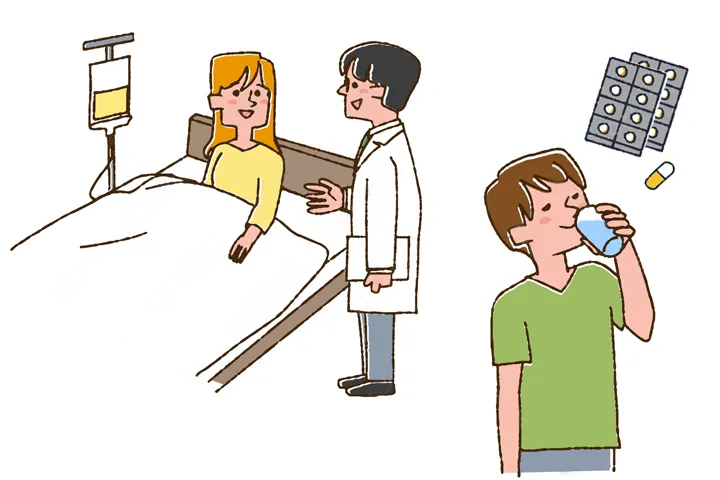ホスト: 今日はですね、ある日突然、こう片方の耳が聞こえなくなるっていう突発性難聴。これについて掘り下げていこうと思います。
ゲスト: はい。
ホスト: 資料としては、EBMから見た突発性難聴の臨床とか、あと難聴耳鳴り診療ハンドブック。こういった専門書を参考にしています。
ゲスト: ええ。
ホスト: いや、もしね、急に耳が聞こえなくなったらって考えると、やっぱり不安ですよね。
ゲスト: そうですね。
ホスト: なので、まあ、何が起きてどう対処すればいいのか。あと、多くの人が悩む耳鳴りとの関係、このあたりをギュッと要点をつかんでいきたいと思います。
ゲスト: はい。
ホスト: では早速ですが、この突発性難聴って、そもそもどういう状態なんですか?
ゲスト: はい。えっと、これは文字通り突発的に、つまり原因がはっきりわからないまま片耳、まあ、ごくまれに両耳のことなんですが、その感音難聴が起こる病気です。
ホスト: 感音難聴。
ゲスト: ええ。音を感じ取る内耳とか、そこから脳へ信号を送る神経、そのあたりに問題が起きて聞こえにくくなる状態ですね。
ホスト: なるほど。
ゲスト: 診断の目安としては、まあ「隣り合った3つの周波数で、それぞれ30dB以上の聴力低下が72時間以内に急激に起こること。」とされています。
ホスト: 72時間以内、結構急ですよね。
ゲスト: そうなんです。突然というのが本当に特徴でして。
ホスト: うーん。発症した瞬間を覚えてる方も多いとか。何月何日何時頃、何をしてた時みたいに。
ゲスト: まさにそういう方が多いですね。朝起きたら聞こえなかったというケースも3割ほどいらっしゃいます。
ホスト: 朝起きたらですか?
ゲスト: はい。で、それ以外にもいくつか症状を伴うことがありますね。
ホスト: はい。
ゲスト: まず耳鳴り。これはもうほとんどの方、9割以上の方に現れます。
ホスト: 9割、ほぼ全員じゃないですか。
ゲスト: そうなんです。 で、音としては「ゴー」とか「ザー」とか、ちょっと濁った感じの音が多い傾向がありますね。
ホスト: うわー、それは辛そうですね。
ゲスト: ええ。それから耳が詰まった感じ。耳閉感って言いますけど、これも約3分の2の方に見られますね。
ホスト: 耳が詰まった感じ。
ゲスト: あとはめまいですね。これも3割からまあ5割くらいの方に伴います。 ただ多くは一時的で、目がぐるぐる回るような激しい回転性のめまいは比較的少ないです。
ホスト: なるほど。一時的ではあれ、めまいもあると。
ゲスト: ええ。
ホスト: ここであの、大事なのは、突発性難聴だと、普通は耳の痛みとか耳だれ、頭痛、熱なんかはないってことですよね。
ゲスト: あ、その通りです。そこは非常に重要なポイントで、もしそういった症状がある場合は、何か別の病気を疑う必要がありますね。
ホスト: なるほど。鑑別のポイントですね。わかりました。 でもやっぱり一番気になるのは回復するのかどうか・・・予後ですよね。
ゲスト: そうですよね。ええ・・・残念ながら全員が元通りに回復するわけではないんですね。
ホスト: うーん。
ゲスト: 回復の見込みに影響する要因っていうのがいくつか報告されてまして、特に重要なのはやはり治療開始までの時間です。
ホスト: 時間ですか。
ゲスト: はい。発症してからできれば7日以内、早ければ早いほど良いとされています。
ホスト: 7日以内。
ゲスト: それから発症時の聴力低下の度合い。これも大きいですね。 特に90dB以上のかなり高度な難聴だと回復はちょっと難しくなる傾向があります。
ホスト: うーん、時間との勝負、そして最初のダメージの大きさ、と。
ゲスト: ええ、そういうことです。他にもめまいを伴う場合とか、あとご高齢の方、それから聴力検査の形で高音域だけがすごく落ちているタイプもやや予後が厳しいかなという傾向はありますね。
ホスト: いろいろあるんですね。
ゲスト: 最近ではMRIのちょっと特殊な撮り方なんですけど、 3Dフレア法っていうので、内耳に異常が見つかると回復が難しい独立した要因だ、なんていう報告もあります。
ホスト: へえ、MRIでもわかることがあるんですね。
ゲスト: ただ、一方で自然に治る方もいらっしゃるので。 治療の効果を正確に見極めるのがちょっと難しい面もあるんですよ。
ホスト: あー、なるほど。
ゲスト: 多くの場合、聴力は発症してから1、2ヶ月でだいたい固定してくることが多いですね。
ホスト: 1、2ヶ月で。では、その治療っていうのはどういうことをするんですか?特効薬がないというのは聞きましたが。
ゲスト: そうですね。確立された特効薬はないんですが、だからこそ早期治療が、まあ非常に重要だと考えられています。 これはもう推奨グレードA。「行うことが強く推奨される」レベルですね。
ホスト: まずは早くということですね。
ゲスト: はい。で、一般的な治療としては、まずステロイド薬ですね。
ホスト: ステロイド。
ゲスト: ええ。飲み薬とか点滴で全身に投与する方法。これは推奨グレードC1。 まあ、「選択肢の一つとして考慮して良い」レベルです。
ホスト: ふむふむ。
ゲスト: それと、鼓膜に注射して直接耳の中に薬を入れる鼓室内投与。ITIって略したりしますけど。
ホスト: えっと・・・直接耳に注射ですか?
ゲスト: そうなんです。ちょっと怖い感じもするかもしれませんけど。
ホスト: ええ、しますね。
ゲスト: このITIは最初の治療としてはC1ですけど、飲み薬なんかで効果が不十分だった場合の追加治療としては、 「行うことが推奨される」推奨グレードBとされています。
ホスト: なるほど、そういう方法もあるんですね。
ゲスト: 全身への副作用が少ないっていうメリットもありますね。他には血流改善とか代謝を促す目的で、ビタミンB12とかATP製剤っていう薬が使われることも多いんですが。
ホスト: はい、よく聞きますね。
ゲスト: 正直なところ、これらが有効だっていう強い証拠、エビデンスはまあ、あまりないんですね。
ホスト: そうなんですか。
ゲスト: ええ。重症例だと、プロスタグランジン製剤、PGA-1という血流改善薬をステロイドと併用することもあります。 これもC1ですね。
ホスト: ほう。
ゲスト: これも発症2週間以内なら有効な可能性があるということで、これも選択肢の一つとされています。
ホスト: へえ、酸素も。
ゲスト: ええ、もちろん安静にしたり、ストレスを避けるっていうのも基本的には大事です。
ホスト: それはそうですよね。
ゲスト: ちなみに、入院と外来とで治療効果に差はあるんですか?
ホスト: あ、それについては明確な差があるという証拠はないとされていますね。これもC1です。
ゲスト: なるほど。 難聴自体も大変ですけど、多くの人がその治療後も悩まされるのが、あのしつこい耳鳴りだと思うんです。9割以上の方に出るんでしたよね。
ホスト: そうですね。非常に多いです。
ゲスト: 難聴が良くなっても耳鳴りだけ残っちゃう場合っていうのはどう考えればいいんでしょう?
ホスト: いや、そこが本当に難しいところでして。耳鳴りの場合、目標は音を完全に消すことよりも、耳鳴りによる苦痛を減らすことに置かれることが多いんです。
ゲスト: 苦痛を減らす?
ホスト: ええ。耳鳴り苦痛モデルっていう考え方があるんですが、簡単に言うとですね、耳鳴りの音自体は聞こえの神経経路、まあ、入力が減ったことによる脳の過活動とか、そういうところで発生するんですけど。
ゲスト: はい。
ホスト: それが不安とか集中とか記憶とか、そういう脳の他の部分と結びついちゃうことで、「うるさいな」とか「気になるな」、「辛いな」っていう苦痛が増幅してしまうというメカニズムですね。
ゲスト: ああー音そのものだけじゃなくて、 脳のなんていうか、反応の仕方が問題になってくるっていうことですか。
ホスト: まさにそういう側面が強いと考えられています。ですから、治療としては、まずこれは危険な信号じゃないんだよ、脳が生み出している音なんだよっていうことを理解してもらうための教育的なカウンセリング。これが基本になります。
ゲスト: まずは理解すること。それだけでもこう不安が減って、悪循環を断ち切る助けになることがあるんですね。推奨グレードとしてはC1ですけど。 非常に重要なステップです。
ホスト: なるほど、理解が大事なんですね。対処法としては他にどんなものが?
ゲスト: 代表的なのは音響療法ですね。
ホスト: 音響療法。
ゲスト: はい。これは周りの環境音をうまく使ったり、サウンドジェネレーターっていう機械で心地よい音を聞いたり、あるいは難聴があれば補聴器を使うことで、耳鳴りの音を目立たなくして、脳がそれに慣れる。 順応するのを助けるという方法です。
ホスト: 補聴器も使うんですね。
ゲスト: ええ。特に補聴器は聞こえにくくなった音を補うことで、耳鳴りの原因かもしれない聴覚路の活動を正常化させるっていうアプローチとしても重要視されています。これは推奨グレード1A、標準的な治療として推奨されていますね。ポイントは、マスキングって言って無理やり音で消すんじゃなくて、 慣れ、順応を促すというところですね。
ホスト: なるほど、慣れることが目標なんですね。
ゲスト: そうです。あとは認知行動療法CBT。これも非常に有効な方法です。これも推奨グレード1Aですね。
ホスト: 心理療法ですか?
ゲスト: ええ、耳鳴りに対して「もうダメだ」みたいな、否定的な考え方とか、耳鳴りを避けようとする行動パターン。そういうのを変えていくことで苦痛を和らげるアプローチです。
ホスト: 考え方を変える、と。
ゲスト: はい。薬については、残念ながら耳鳴りの音自体を小さくする効果はあまり期待できないんですね。推奨グレードも2C。推奨しないレベルです。
ホスト: あ、そうなんですね。
ゲスト: ただ、耳鳴りに伴って不眠とか不安、うつ状態がすごく強い場合に、それらを和らげる目的で補助的に使われることはあります。
ホスト: なるほど、あくまで補助的にですか。よくわかりました。 じゃあ、まとめると、突発性難聴っていうのは、原因はわからないけれども、とにかく早く治療を始めるのが大事だと。
ゲスト: はい。
ホスト: そして、たとえ耳鳴りが残ってしまったとしても、音そのものに注目するんじゃなくて、カウンセリングとか音響療法、認知行動療法なんかで、それによる苦痛をマネジメントしていく、と。そういうアプローチが中心になるわけですね。
ゲスト: まさにおっしゃる通りです。よくまとめていただきました。
ホスト: いえいえ。
ゲスト: 最後に一つだけちょっと皆さんに考えてみてほしい問いかけなんですけど。
ホスト: おお、何でしょう
ゲスト: 今日の話にあった耳鳴り苦痛モデルを考えるとですね、もし普段から例えばストレスへの対処法を身につけていたり、感情の波をうまく乗り越える練習をしていたとしたら。
ホスト: はい。
ゲスト: 万が一突発性難聴になった時、あのーの耳鳴りの苦痛の度合いって もしかしたら、発症する前からある程度コントロールというか、軽くできる可能性ってあるんでしょうかね。
ホスト: ああ、なるほど。脳の準備というか。
ゲスト: ええ。脳のネットワークって本当に複雑ですからね。そういうつながりについて、ちょっとだけ思いを巡らせてみるのも面白いかもしれないなと。
ホスト: 深い問いですね。確かに、考えてみる価値がありそうです。
※出典1 SCOM・033 金原出版「EBMからみた突発性難聴の臨床」
※出典2 中山書店「難聴・耳鳴り診療ハンドブック|最新の検査・鑑別診断と治療」